西八代郡
市川三郷町(旧西八代郡市川大門町/旧西八代郡三珠町/旧西八代郡六郷町)
【旧西八代郡市川大門町】江戸時代,日本三大花火といわれた甲斐大門の花火の光景を描いています。これを現代に復活させた「明神の花火大会」は笛吹川に掛かる三郡橋と富士川大橋の間で打ち上げられるということですが,これらの橋は現代的なもので蓋に描かれているものとは似ても似つかないものです。両側には障子が描かれていますが,旧市川大門町は和紙(市川手漉和紙)の生産が盛んで中でも障子紙は全国のトップシェアを誇るとのことでした。

2016/06/06
【旧西八代郡市川大門町】上部に旧町章,その下に「消火栓」の文字が入った消火栓蓋3種。上左は丸型,上右は受枠に「T」の字が入っていて,本体は長方形です。下も長方形型ですが,受枠も本体も角丸になっています。

2016/06/06
【旧西八代郡市川大門町】小型の制水弁の蓋です。中央部は斜め格子模様に旧町章と「制水弁」の文字,外側はドット模様で青色に彩色されています。

2014/05/20

2014/05/20
【旧西八代郡三珠町】旧町の木:アカマツは描かれていませんが,外周上部にある紐のようなものは,旧町の花:フジだと思われます。そして中央に大きく描かれているのはボタンですが,下部に見える「歌舞伎の里」のいわれである初代市川團十郎ゆかりの歌舞伎文化公園には約120種類2000本ほどのボタンが植えられていて,毎年春には「ぼたんの花まつり」が催されるそうです。そして何故ボタンなのかというと,市川家の替紋だとか,江島生島事件の江島が二代目團十郎に送った着物の柄に由来するとか……。ちなみにボタンの由来を探っていろいろ検索していると「市川團十郎発祥の地」という言葉が出てきて,現地にはこの文言が刻まれた碑があるのだとか。なんか違和感があってさらに調べてみたら「発祥」には「天命を受けて天子となるめでたいしるしが現れること。帝王やその祖先が生まれ出ること」というのが第1義なのだそうです。この歳になって,目から鱗が一枚落ちました。
右の親子蓋も同じデザインです。
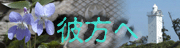



 前の蓋
前の蓋  ホーム
ホーム  蓋の模様
蓋の模様 どっかの蓋
どっかの蓋  上へ
上へ 下へ
下へ
